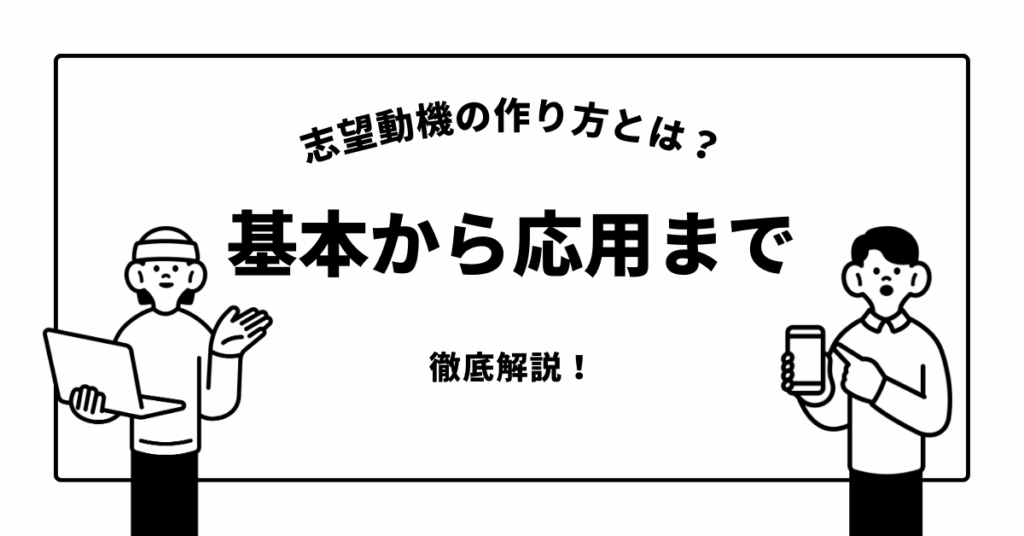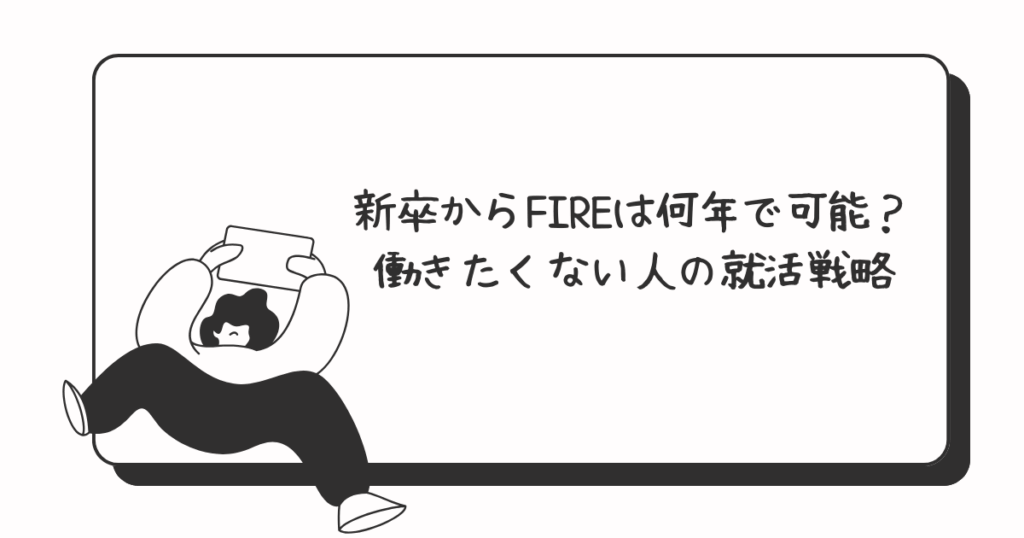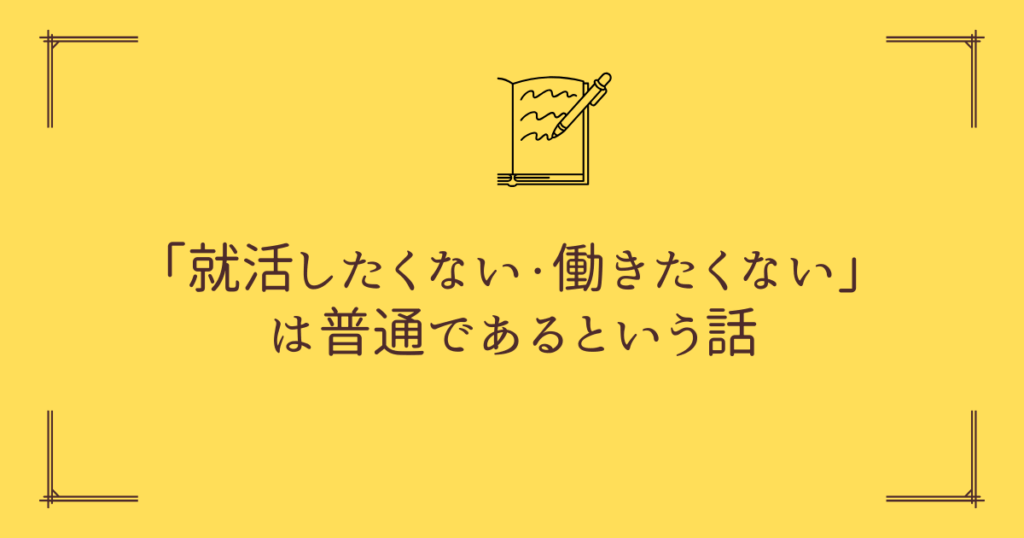
就活を始める時期になると、まわりが「第一志望はどこ?」「説明会行った?」などと口にし始めます。
そんな空気の中で、「正直、働きたくないんだよな……」と感じている自分に、どこか罪悪感を覚えている人も多いはずです。
しかし、その感情は全くおかしなものではありません。
むしろ、自分と向き合っているからこそ出てくる自然な気持ちです。
この記事では「就活が面倒くさい」「そもそも働きたくない」「でも、どこかには就活しないと、取り残されてしまう」と悩む人のために、どのように就活を進めるべきか「戦略的」に考えてみます。
働きたくないと思うのは変じゃない

働きたくないと感じるのは「怠けたい」とか「甘えている」からではなく「この先何十年も働くという前提に納得できていない」からです。
その違和感を抱くことは、むしろ感性が鋭く、真剣に生きようとしている証拠です。
誰かと同じゴールを目指す必要なんてありません。
大切なのは、その違和感にフタをしないことです。
「働きたくない」という気持ちをネガティブなものとしてではなく「自分らしく生きたい」という前向きな意思と捉えることが、就活を意味あるものに変える第一歩です。
「働きたくない」と検索する時点で、就活への違和感を抱えている証拠
「就活 働きたくない」とGoogleで検索している時点で、あなたは「何かがおかしい」と感じているのだと思います。
ただ漠然と「会社に行きたくない」「組織で働くのが想像できない」といったレベルではなく、その背景には「就活という仕組みに対する違和感」や、「みんなと同じことをしていて本当にいいのか?」という深い問いがあるはずです。
多くの人が疑問を持たずに就活に乗っかるなかで、自分の人生をちゃんと考えて立ち止まれるあなたは、むしろ「感度が高い人」です。
問題なのは「疑問を抱くこと」ではなく「それに向き合わず流されてしまう」ことです。
検索というアクションを取った時点で、あなたは「自分の人生に責任を持とうとしている」のだと思います
周囲は前向きな就活ばかりだけど、自分だけモヤモヤしているように感じる
就活が本格化すると、まわりは「自己分析やった?」「面接の準備進んでる?」と前向きな話題で盛り上がり始めます。
その輪に入れない自分を、どこかで「ズレてるのかな」と感じることもあるかもしれません。
でも、その「モヤモヤ」はとても大事な感覚です。
それは「このまま就職していいのか」「働くって本当に必要なことなのか」といった、根本的な疑問から生まれるものです。
多くの人が気づかないまま見て見ぬふりをして進んでいくのに対し、あなたはその違和感をちゃんと認識できている。
それは、自分の価値観や人生観を持っている証拠です。その感覚を無理に打ち消す必要はありません。
むしろ、その違和感の正体を見つけにいくことが、就活の本当の意味に近づく鍵になります。
でもその違和感は、実は無思考なレールへの拒絶反応
私たちは、小さい頃から「いい大学に入って、いい会社に就職するのが正解」というレールの上を走るように育てられました。
でも、いざ自分がその「正解ルート」に足を踏み出そうとしたとき、「このままでいいのか?」と違和感を覚える人もいます。
その違和感の正体は、「働きたくない」というよりも「思考停止で働くのが嫌だ」という感情かもしれません。
つまり、ただ「働きたくない」という気持ちではなく、「誰かに決められた人生をそのままなぞりたくない」という拒否の感情です。
それは怠惰でも、ネガティブでもありませんし「厨二病かよ」で片付けて良いものでもありません。
むしろ「自分の人生を自分で決めたい」という健全な意思表示です。
この拒絶反応を「甘え」ととらえるのではなく「探究心」だと考えると、自分の立ち位置が明確になります。
今あなたが感じている違和感は、「自分らしい人生を探したい」という欲求の裏返しなのです。
就活=一生働くための第一歩…じゃなくていい

就活という言葉には、どうしても「これから何十年も働く未来への入り口」という重たいイメージがついて回ります。
そのため、「今ここで会社を選び間違えたら終わりなんじゃないか」「この一歩で一生が決まるのではないか」と感じてしまう人は多いです。
でも、本当にそうでしょうか?
実際の社会では、最初に入った会社で定年まで働く人は、もはや少数派です。
転職、副業、独立、リスキリング……働き方は年々多様になっており、「就職」はゴールでもなければ、絶対に守るべき正解でもありません。
つまり、就活は「一生働くための契約」ではなく「ひとまず社会に出る手段」としての選択肢なのです。
完璧な会社を探すのではなく、「今の自分が経験を積めそうな場所」を選ぶだけで十分です。
正社員になること=一生その道に縛られる、と思っていないか?
多くの就活生が「正社員になる=その会社に骨を埋めること」だと思い込んでいます。
「内定=一生の決断」というプレッシャーがのしかかり、本来なら「自分がどんな経験を積みたいか」を考える時間さえ奪われてしまう。
でも実際には、社会人の多くが数年で転職を経験していますし、キャリアは何度でもやり直せます。
正社員になることは、ひとまず安定した収入を得て、自分の選択肢を増やすための「一時的な手段」であって構いません。
むしろ、1社目で「自分に合わない働き方」を体感した人のほうが、その後の選択に迷いがなくなるというケースも多いです。
会社に合わせるのではなく、自分の人生の軸を育てることを優先していいのです。
今は「正社員→転職→副業→独立」も当たり前の時代
昭和〜平成初期と違い、今は「働き方の正解」が1つではありません。
会社員から副業ライターへ、営業職からYouTuberへ、店舗勤務からフリーランスへ──あらゆる働き方の「行き来」が普通に行われるようになっています。
つまり「1社目で一生が決まる」時代はもう終わっています。
それなのに、就活の現場ではいまだに「3年続けなければならない」といった古い価値観が残っているため、就活生は「キャリアを決定づける選択」というプレッシャーにさらされてしまう。
でも本当は、社会に出た後のほうが選択肢は広がっていくのです。
就職はゴールではなく、あくまでスタートライン。
そしてそのスタートラインさえ、あとで引き直すこともできます。
働きたくないと思っている人ほど、この「可変性のある働き方」を前提に就活と向き合った方が自分の理想に近づける可能性が高いです。
就職は「経済的自立」のための「ひとまずの選択肢」でしかない
もしあなたが「できれば働かずに生きていきたい」と思っているのなら、まず考えるべきなのは経済的な自立です。
つまり、実家に頼らず、自分で生活費を稼ぎ、将来に向けて資産を築いていく力をどう得るかということ。
その手段のひとつとして「就職」という選択肢があるにすぎません。
働きたくない=ずっと親に依存する、ということではないはずです。
あなたはおそらく「働くなら納得できる理由が欲しい」「無理して頑張る人生は嫌だ」と思っているのではないでしょうか。
就職は「自分の選択肢を増やすためのチケット」と考えればいいのです。
働きたくないと思うなら、その気持ちを否定する必要はありません。
ただ、自立して生きていくために、今どんな選択が現実的なのかを考えることが、いちばん誠実な行動です。
働きたくない人ほど、就活では「ズレたこと」を言ってはいけない

「働きたくないけど就活はしないといけない」──この気持ちを抱えたまま面接に臨むと、つい本音が出てしまいがちです。
たとえば「将来的には独立したい」「できれば早く資産形成を終えてリタイアしたい」など、FIRE的な価値観をそのまま口にしてしまうと、面接官には「すぐ辞めそうな人」という印象を与えてしまいます。
働きたくないという気持ちがあるからこそ、就活では「相手の期待とのズレ」を意識的に調整する必要があります。
本音をそのまま言うことが誠実だとは限りません。
自分の価値観と、企業が求める人物像の「交差点」探す力こそが、就活で評価される視点です。
そしてそれができる人こそ、働き方に悩む人のなかでも、一歩抜きん出ることができます。
「FIREしたい」「3年で辞めたい」など、本音すぎる主張は通用しない
就活の場では「正直に話すこと」が推奨されるように見えて、実は「相手にどう受け取られるか」の配慮が非常に重要です。
面接官は自社で数年かけて人を育てたいと思っています。
あからさまに「すぐ辞めたいです」「給料のために働きます」などと言ってしまえば(もしくは伝われば)、当然マイナス評価になります。
たとえ本心がFIRE志向でも、それをストレートに伝えるのはNGです。
企業は「組織の一員として活躍してくれるかどうか」を見ており、自己都合の強い主張は「協調性がない」「成長意欲がない」と受け取られる可能性が高いからです。
正直さ=誠実さ、ではありません。
「戦略的な伝え方」をすることが、社会人としての成熟度を示す方法でもあるのです。
面接官は「育てる前提」で見ているので、すぐに辞めそうな人は敬遠される
企業が新卒を採用するのは「「長期的に活躍してもらいたい」」という前提があるからです。
そのため、どんなに能力が高くても、「この人は短期間で辞めそうだな」と思われてしまうと、採用には至りません。
これは人事の立場になって考えれば、ごく当然のことです。
働きたくないという気持ちが強く出すぎると、「会社の一員として成長していく姿」がイメージできなくなります。
たとえ本人にやる気があっても、発言の内容が「早期退職」を連想させるものだと、面接官はリスクを感じてしまうのです。
大切なのは、自分の将来像を企業の中でどう描くかを具体的に語ること。
たとえ心の奥底に別のゴールがあっても「目の前の仕事にしっかり取り組む姿勢」を見せることが、選考通過には必要不可欠です。
自分の価値観を伝えつつ、組織で働く意義を理解していることを見せる必要がある
就活で評価されるのは「自分の考えを持っている」ことと、「その考えを社会の中でどう活かすかを理解している」ことの両立です。
つまり「私はこういう価値観を持っている」だけでは不十分で、「それを踏まえたうえで、御社ではこういう働き方ができると考えています」と語れるかどうかがポイントになります。
働きたくない=組織が嫌い、という印象を与えがちですが、就活では「協調性」「柔軟性」も見られています。
そのなかで自分の個性や価値観を表現するには、「相手の立場を理解したうえで伝える力」が求められます
- 「FIREを目指しているからこそ、最初の会社ではビジネスの土台をしっかり学びたい」
- 「将来的に自由な働き方をしたいので、そのためにまず組織の中で自分を鍛えたい」
こういった伝え方なら、本音を押し殺さずに、面接官も納得してくれるでしょう。
自分にとっての「働く意味」を考えてみよう
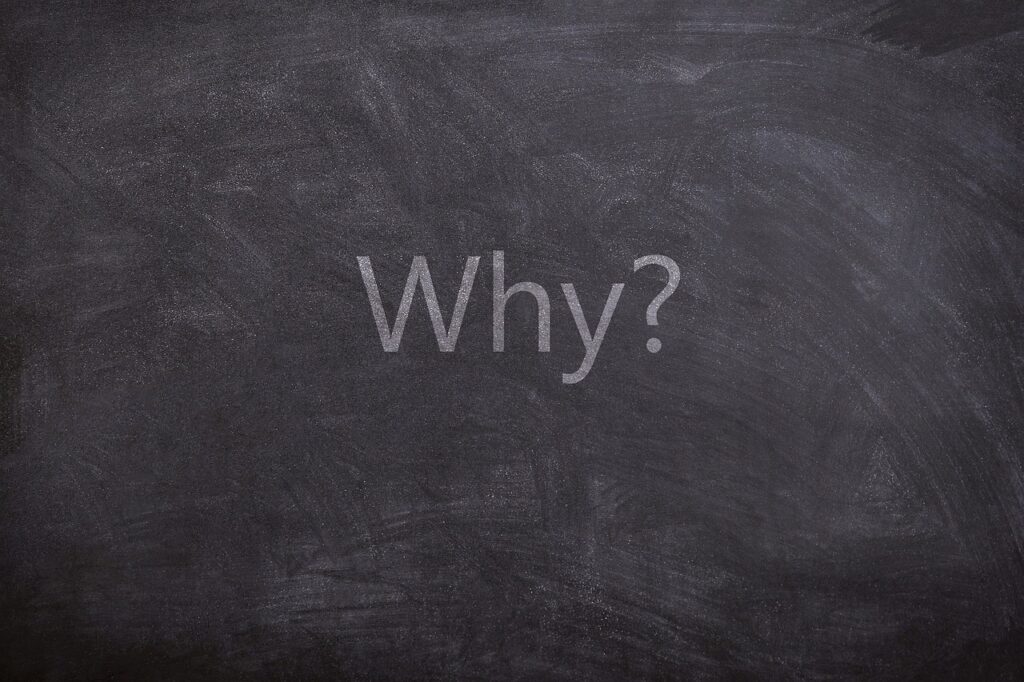
「働きたくない」と思っているときほど、一度立ち止まって「それならば、自分は何のために働くのか?」を考えてみてください。
他人に言われた正しさや、社会の「当たり前」に流されず、自分の中にある「働く理由」を明確にすることは、就活において最も強い武器になるからです。
「働きたくない」という感情は、ただの拒否反応ではありません。
その裏側には「納得できない働き方をしたくない」「自分にとって意味のある時間を過ごしたい」という前向きな意志が隠れています。
つまり、「働くこと」自体が問題なのではなく、どんなふうに働くのか、何のために働くのかが曖昧だからこそ、不安や嫌悪感として現れているのです。
ここでは、自分の中にある「働く意味」を探るための視点を紹介していきます。
それによって、就活における言葉選びや企業選びが、より自分軸でできるようになるはずです。
お金のため?成長のため?社会的信用?自分の中の優先順位を整理する
働く理由とひとくちに言っても、人それぞれです。
- 「生活費を稼ぐため」
- 「将来のためにスキルを身につけたい」
- 「親を安心させたい」
- 「世間体を保ちたい」
など、さまざまな目的が交差しています。
しかし、大事なのはそれらを「他人基準」ではなく「自分の本音」で整理することです。
本当はお金がすべてだと思っているのに「成長したい」と言い換えてしまう人は少なくありません。
就活では建前が求められる場面も多いですが、軸まで嘘をついてしまうと、自分自身が疲弊してしまいます。「お金が大事」でも「なるべく働かずに生きたい」でもかまいません。
その本音を見つけたうえで、「その考えを実現するには、まずどんな選択が必要なのか?」と逆算できるようになると、就活の見方も変わります。
働く意味が「FIREのため」でもいい
「なるべく早く経済的に自立して、働かなくても生きていける状態をつくりたい」
それがあなたの働く理由であれば、堂々とFIRE志向を持てばいいのです。
重要なのは、そのビジョンに対してどれだけ現実的なプランを立てているかという点です。
たとえば
- 「FIREを実現するために、まずは月収を安定させたい」
- 「副業が許される企業に入り、キャリアを積みながら資産形成を進めたい」
そうした具体的なステップを持っている人なら、FIRE志向であること自体が「自立心」や「計画性」として評価される可能性もあります。
つまり、FIREを理由にしてもいい。
ただし、それを「逃げ」ではなく「戦略的な選択」として語れるようにすることが大切です。
働きたくないという感情も、明確な目標のもとで発信すれば、むしろ説得力のある自己PRに変えることができます。
問題は「なぜその会社で働くのか」を言語化できるかどうか
どれだけ本音を持っていても、面接では「なぜこの会社を選んだのか」を説明できないと通過できません。
FIRE志向であろうが、働きたくない気持ちがあろうが、企業側は「この人はうちで頑張ってくれるか?」を知りたいのです。
そのためには、自分の価値観と企業の特徴をどこで接続するかを考える必要があります。
たとえば
- 「御社のように効率を重視し、生産性の高い働き方を評価する環境に惹かれました」
- 「自己裁量が大きく、働き方の自由度が高い点が、自分の将来像と一致しています」
というように、自分の軸を無理に変えるのではなく、企業と重なるポイントを抽出して伝えることで、自然な志望動機を作ることができます。
「働きたくない」と思っているからこそ、自分が働いてもいいと思える条件を具体化することが、就活を突破する上で不可欠な作業です。
自由を重視する人向けの志望動機の書き方

「できるだけ縛られずに働きたい」「時間や場所にとらわれたくない」──そう感じる就活生は、今や珍しくありません。
しかし、企業の採用担当者にとって自由を求める発言は「わがまま」「協調性がなさそう」とマイナスに受け取られるリスクもあります。
では、どうすれば自分の価値観を大切にしながら、就活を突破できるのでしょうか?
ポイントは自由を「目的」にするのではなく、「目的を果たすための手段」として語ること」です。
また、自由を求める理由の裏にある、自分なりの努力や意志をセットで伝えることで、説得力を持たせることができます。
ここでは、自由を重視する就活生が使える志望動機の作り方と、具体的な伝え方を紹介します。
自由を求める理由には「自立したい」があることを伝える
自由を求めることは、イコール「楽をしたい」という意味ではありません。
本質的には、「誰かに命令されるのではなく、自分の意思で選択して生きたい」という自立志向の表れです。
そのため、志望動機では「自由に働けるから魅力を感じました」だけでは不十分です。
- 「自由であることに責任が伴うことも理解しており、自分で考えて動く力を高めたい」
- 「裁量がある環境に身を置き、意思決定を繰り返すことで、自分の判断力を磨きたい」
といった表現を入れることで、単なる甘えに見えるリスクを回避できます。
自由を選ぶ=自分で責任を持つ、という姿勢を明確にすることで、企業側も「この人なら任せられるかもしれない」と感じるはずです。
本音と建前を切り分けず、「共存」させる構成にする
「本当は働きたくない」「FIREを目指している」
そうした本音を押し殺して優等生的な志望動機を書こうとすると、言葉に熱が乗らず、結果的に面接官の印象にも残りません。
大事なのは、本音を完全に隠すのではなく、建前と混ぜて納得感のある動機として再構成することです。
たとえば、
「将来的に自由な働き方を目指しています。そのためには、まずビジネスの基礎を現場でしっかり学びたいと考え、御社を志望しました」
というように、最終的なビジョンに向かって努力する意志を示せば、本音が悪印象にはなりません。
自由を求める人は、目標から逆算して今のステップを正当化できる人です。
それに、最近のこの風潮です。
「定年までずっと居ると約束できないなら採用しない」なんて企業はありません。
あったら超絶地雷なので、面接の途中で帰りましょう。
このように、思考の過程を示すことで、「ちゃんと考えて行動できる人」として評価されやすくなります。
自由な環境に惹かれたことよりも、「その中でどう成長したいか」を語る
就活生の多くが「裁量がある」「若手にもチャンスがある」という言葉を使いますが、実はそこに説得力がある人は少ないです。
面接官は「自由な環境に惹かれた」という理由よりも「そこで何を得ようとしているのか」を知りたがっています。
たとえば、
- 「御社のように個人の裁量を重視する環境で、自分の思考力と判断力を試したい」
- 「自由な環境だからこそ、成果に責任を持つ姿勢が求められると理解しています」
というように、環境の魅力だけで終わらず、その環境下での自分のあり方や成長イメージまで語ることが、信頼感につながります。
自由を魅力に感じるのは当然のことです。。
大事なのは、その自由をどう使っていきたいのか、どんな責任を担う覚悟があるのか。
そこまで含めて言葉にすることが、面接での伝わり方を大きく変えるポイントです。
「働きたくない」のその先へ

「働きたくない」と感じるのは一見ネガティブな感情のように思えますが、実は人生をどう生きたいかを真剣に考えている証拠です。
そして、就活を通じて向き合うべきなのは「働きたくない」という気持ちを否定することではなく、その感情の奥にある本当の望みを見つけることです。
「働きたくないから就活したくない」という思考で止まってしまうと、選択肢が極端になります。
そこで「働きたくないからこそ、自分で納得できる働き方を探したい」と視点を変えれば、就活は自由の入口にもなり得ます。
ここでは、「働きたくない」という感情からスタートして、その先にどう進むかを考える視点を提示します。
働くのは手段。自分の人生を豊かにするためにどう動くか
働くことそのものに価値を見出せないとき「なぜ働くのか?」という問いに答えるのは難しくなります。
しかし、働くことは手段であると割り切れば、考え方が変わります。
お金を稼ぐのも、スキルを得るのも、キャリアを積むのも、最終的には自分の望む人生を実現するためのステップでしかありません。
つまり「嫌なことを我慢して続ける」必要はないけれど「人生をより自由にするために、いま必要な経験を積む」という発想なら、就活も意味のあるものになります。
働きたくない気持ちは否定せず、うまく付き合っていく。
そのための自分なりの働き方を模索する姿勢こそが、現代の就活においてもっとも大切な要素だといえます。
一度就職してみることで、逆に「働かない人生」への道筋も見えてくる
「働きたくないなら、そもそも就活なんてしない方がいいのでは?」と考える人もいるかもしれません。
でも、実はいったん働いてみることが、自由を手に入れる最短ルートになるケースも多いのです。
実際に会社で働いてみれば、「ここは向いてる/向いてない」「自分はどんな環境なら続けられるか」など、肌感覚でわかってきます。
また、給料・社会保険・人間関係・スキル・時間の使い方など、働かないと見えないリアルもたくさんあります。
FIREや独立といった働かない選択肢を目指すにも、最初は安定した収入や社会経験がベースになります。
つまり「働くことを1回経験する」ことで、逆に「働かずに生きる方法」が現実味を帯びてくるのです。
最初からすべてを拒絶するより、一歩踏み出して素材を手に入れたほうが、自由への道筋を描きやすくなります。
働きたくないなら、働かずに生きる準備を始めること
もし本当に「働きたくない」という気持ちが強いなら、ただ言葉にして終わらせるのではなく、働かずに生きるための戦略を具体的に考える必要があります。
そのためには
- どのくらいの資金があれば生活できるのか
- 毎月の生活費はいくらで、何を削減できるのか
- どんな収入源をつくれば、労働に依存しなくて済むのか
といったことを、リアルにシミュレーションしてみることが大切です。
SNSやメディアでは「FIREは簡単にできる」といった甘い情報も流れていますが、現実はそう甘くありません。
でも、だからこそ、今のうちから自分の理想に向けて少しずつ準備を始めることが、誰よりも早く働かない選択肢に近づく手段になります。
そして、その準備の一歩として、「今のうちに社会で経験を積んでおく」という考え方は非常に合理的です。
嫌々働くのではなく「嫌にならない働き方を見つけるために、今行動する」というスタンスが、現実と理想のバランスを取る鍵になります。
結局「FIREしたいならいくら必要か」は以下の記事で解説しています。
より具体的に自分の状況を反映させてシミュレートしたい場合、↑の記事を軽く読んで自分でまとめた情報をChatGPTに投げてみてください。
あなたのFIRE戦略を一緒に考えてくれます。
(ただし、人生に関わることなので、最終的な決定や細かい数値は自分で考えて、計算してください)
迷いがあるからこそ、自分のための就活を
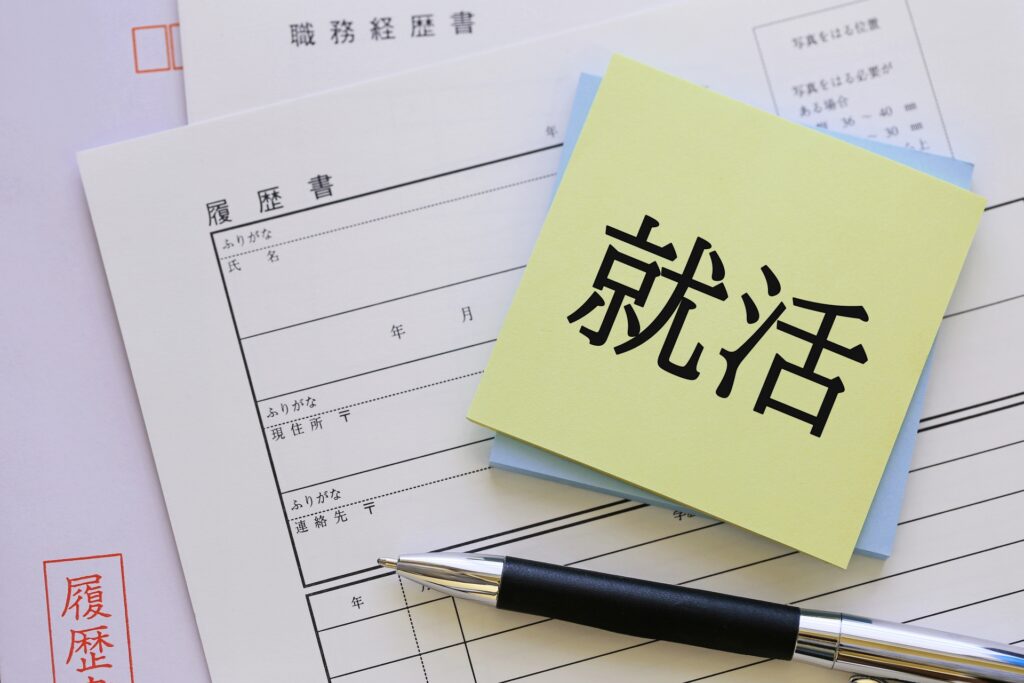
「働きたくない」「就活したくない」
そう感じているあなたは、決して怠け者でも、現実逃避しているわけでもありません。
むしろ、自分の人生に対して真剣だからこそ、納得できない選択を避けたいという気持ちが出てくるのです。
誰かが決めた「正解」に無理やり合わせるのではなく、自分なりの納得解を探そうとすること。
それこそが、自分のための就活の第一歩になります。
この章では、就活を通じて自分の人生を見つめ直すヒントを、最後に改めて整理していきます。
他人と同じゴールを目指す必要はない
まわりの就活生が「大手に行きたい」「安定した職に就きたい」と口を揃えるなか、自分だけが働くことにモヤモヤしている──そう感じるのは自然なことです。
でも、人生の正解は人それぞれです。
誰かにとっての成功が、自分にとっての幸福とは限りません。
だからこそ、「働きたくない」という感情を持っているなら、それを隠さずに自分なりの価値観として整理していくことが大切です。
それができれば、たとえまわりと違う選択をしても、自分の中ではブレずにいられます。
他人と比較するのではなく、自分の納得感を軸に動ける人が、結果として強くなっていきます。
就活は社会に出るための準備であって、人生の正解探しではない
就活というイベントは、時に「人生を決める大事な勝負」として捉えられがちです。
たしかに最初の選択は大切ですが、それがすべてを決めるわけではありません。
現実には、入社後に気づきを得て転職したり、自分の働き方を変えていく人が大勢います。
就活はあくまで、「どうやって社会に出てみるか」という準備プロセスです。
ゴールではなく、最初の地点にすぎません。
だからこそ、完璧な答えを見つけるよりも、「自分が今納得できる選択」をすることの方が大切です。
気負いすぎず、焦らず、自分のペースで進めばいいのです。
【結論】働きたくない気持ちを持ったままでも、前向きな一歩は踏み出せる
「働きたくない」という気持ちを持っている人は多いですが「そんな甘えたことを言っていられない」とその気持ちを抑え込みがちです。
しかし、大切なのは、その気持ちを認めたうえで「じゃあ、自分にとっての納得できる働き方って何だろう?」と考えること。
答えがすぐに見つからなくても、まずは1歩動いてみること。
その一歩が、自分で人生を選ぶ力を育ててくれます。
「働きたくない」からこそ、働き方にこだわる。
そんなあなたにこそ、未来を選ぶ力があります。
だから、恐れずに「自分のための就活」を始めてみてください。